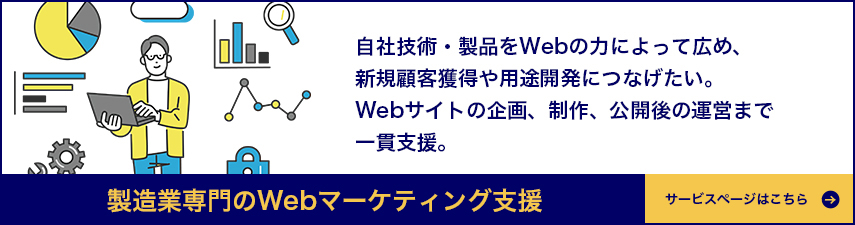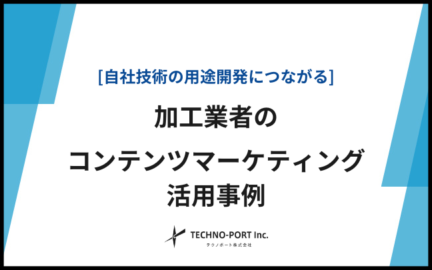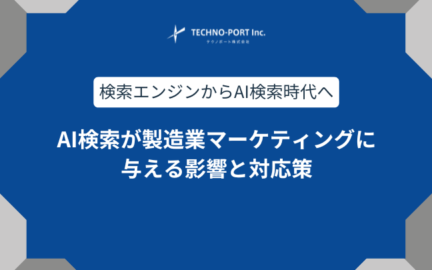Webサイトのアクセスを増やすための方法として当たり前となったSEO対策。しかし対策に力を入れれば入れるほど、Webサイト運用の本来の目的であった「新規顧客の獲得」ではなく、検索上位表示が目的化してしまっているケースが多いように感じます。目的を見誤ってしまうと、Webサイトが手間ばかりかかって売上を稼げない「ダメ営業マン」のようになってしまいます。
この記事の目次
SEOキーワード選定3つのポイント
「アクセス増=問い合わせ増」ではない
多くの企業では、「アクセス数を増やせば自然と問い合わせも増える」と考えがちです。しかし実際には、アクセス数が増えても成果に結びつかないケースが少なくありません。SEOの本質は「量」ではなく「質」であり、見込み客となり得るユーザーに適切にリーチできているかが重要です。弊社が今までに関わったWebサイトの中にも、月間のアクセスが2,000~3,000件あっても数万円しか売上をあげることのできない効率の悪いWebサイトもあれば、月間アクセス300~400件であっても毎月数百万円を稼ぎ出す高効率なWebサイトもありました。
例えば「金属加工」という一般的なキーワードで上位表示を狙ったとしても、情報収集段階の学生や一般ユーザーのアクセスの可能性が高く、本来狙うべき「発注検討中の購買担当者」からのアクセスを集められない恐れがあります。
製造業のSEOで成果を出すには、アクセス数の増減だけに一喜一憂するのではなく、問い合わせや引き合いといったビジネス成果につながるキーワードを選定することが必要です。つまり、「どのユーザーに見てもらうか」こそがSEOの本質なのです。
製造業の購買プロセスとキーワードの関係
製造業における購買プロセスは、他業種に比べて検討期間が長く、複数のステークホルダーが関与するのが特徴です。そのため、検索で使われるキーワードも「情報収集段階」から「比較検討」「最終発注」に至るまで段階的に変化していきます。
ステンレスの板金加工を例にとって説明します。素材をどれにするか、検討する場合は、最初は「ステンレス 特徴」、「ステンレス 加工方法」といった一般的な調査キーワードが使われます。次に「ステンレス薄板 曲げ加工 事例」、「ステンレス溶接 精度」といった具体的な加工方法や、技術比較の検索に移行します。そして最終的に「ステンレス加工 会社 東京」「ステンレスアングル製作 見積り」といった発注直結のキーワードに至ります。
このように、購買プロセスに合わせて必要な情報を提供できるかどうかが、製造業SEOの成否を左右します。単に上位表示を目指すのではなく、顧客の検討段階に応じたキーワードとコンテンツをそれぞれ設計してコンテンツを用意する事が不可欠です。
製造業WebサイトにおけるSEOの重要性
弊社では、売上向上のためのSEOキーワード選定を行う上で、下記の3つの点に気をつけています。
- 最低限のアクセスが稼げるか ・・・ 最低限アクセスを集められるポテンシャルがあるか
- コンバージョンする(問い合わせにつながる)か ・・・ 仕事につながるキーワードかどうか
- 自社の強みと合致するか ・・・ そのキーワードで集客した際に、自社の強みは他社よりも優位性があるか
1、最低限のアクセスが稼げるか
いくらニッチで有効なキーワードでも、検索される回数が極端に少なければ成果につながりにくくなります。SEO施策では、一定の検索需要があるキーワードを選ぶことが前提条件です。この「最低限」がどれくらいなのかは、業種にもよりますが、関連キーワードを含めて月間100件程度の検索需要があるキーワードを選ぶことをおすすめします。
ニッチいくらキーワードを選定しても最低限の検索需要がないケースもあります。その場合はロングテールのキーワードを多数集める手法を取ります。最近では検索のフレーズに多数のキーワードを使用するユーザーも増えてきていますので、いくつかの組み合わせによって検索需要の少なさをカバーします。組み合わせるキーワードは、以下のようなカテゴリを使用するとわかりやすいです。
- 材質
- 加工方法
- 条件
- 業界
- その他
上記を使ったもので例を挙げると
- ステンレス 板金加工 小ロット(材質 × 加工方法 × 条件)
- 板金加工 厚板 納期短縮(加工方法 × 条件 × 条件)
- 自動車部品 プレス加工 OEM(業界 × 加工方法 × 条件)
- 精密板金加工 ISO9001認証 東京(加工方法 × 条件 × その他)
といった形です。検索のフレーズは3つの掛け合わせで例を上げていますが、SEO対策をする場合はこれらの複数のカテゴリを盛り込んでおけば、1つのフレーズの検索需要が少なくても最低限のアクセスは稼げるようになります。
2、コンバージョンする(問い合わせにつながる)か
購買フローの中のどの段階にいるかで、コンバージョンするキーワードもコンバージョン率も変わってきます。一般に情報収集段階ではコンバージョンは低く、発注直前はコンバージョン率が上がる傾向にあります。
ただ、情報収集段階のユーザーがコンバージョンしないかというとそうではありません。情報収集段階のユーザーには技術資料や自社のノウハウのホワイトペーパー、比較検討段階のユーザーには自社製品のカタログなどを用意することで、コンバージョン率を高められます。大切なのは検索意図ごとにコンテンツ化し、それに応じたSEOキーワードを選定することです。
3、自社の強みと合致するか
これを調べるためには、対策したいキーワードで検索した時に1ページ目に表示される競合サイト(会社)を何社かピックアップします。ここでピックアップした会社は、実際にユーザーがアクセスしてきた際に比較検討を行う可能性が非常に高い会社です。これらの会社と自社とを比較した際に優位性が発揮できるかどうかが評価軸となります。
注意点として、顧客のニーズはどのようなものかを理解した上で自社と他社を比較することが挙げられます。顧客が求めていないもので争っても何の意味もありません。
KPI(重要評価指標)を設定する
3つのポイントは理解できましたでしょうか?この3つのポイントは、それぞれKPIとすることができます。
- 最低限のアクセスが稼げるか → KPI:アクセス数
- コンバージョンする(問い合わせにつながる)か → KPI:アクセス数に対する問い合わせ率
- 自社の強みと合致するか → KPI:問い合わせ数に対する受注率
この3つのKPIを追うことで、対策しているキーワードの何が悪いのかを3つの評価ポイントを前提に分析できます。また、下記のようにどの指標が悪いかによって、対処法が異なります(対処法は一例です)。
アクセス数が稼げていない場合
まずは対策キーワードで上位表示ができているかを確認します。上位表示できているのにアクセスが稼げていない場合は、①クリック率(クリック数/表示数)が悪いか、②キーワードの検索ボリュームが低い、のどちらかが原因です。
①のクリック率についてはサーチコンソール、②のキーワードの検索ボリュームは「ラッコキーワード」や「UberSuggest」などで確認ができます。
①の場合はタイトルや説明文の見直し、②の場合は違うキーワードで対策を行う、などの対処法が考えられます。
コンバージョン率(問い合わせ率)が悪い場合
ランディングページ(検索してから初めに閲覧するページ)の直帰率が高く、他ページへの遷移ができていない場合や、検索意図と自社のコンテンツがマッチしていない場合が多いです。ランディングページの内容を見直したり、他ページへ導線するような仕掛け(バナーを設置するなど)を考えたりしてみましょう。そのほかにも問い合わせフォームの項目が多かったり、入力しにくかったりするなどが影響している場合もあります。下記記事を参考にフォームを一度見直してみましょう。
受注率が悪い場合
営業体制が整っていない(メール返信や見積り提出が遅い、など)場合も多いですが、ユーザーのニーズと自社が売り出したい強みにズレが生じている可能性があります。この場合は、イチから戦略(企画)を見直す必要も出てきます。
最新SEO動向と製造業サイトへの影響
これまでは一般的なSEO対策キーワードの選定について説明してきましたが、近年ではAIの登場によってSEO対策のキーワード選定にも新たな対策が必要になってきています。
AI検索・対話型検索への対応
近年のSEOでは、GoogleやMicrosoftをはじめとする検索エンジンがAIを積極的に導入し、従来の検索結果一覧だけでなく、生成AIによる要約や対話型の回答が主流になりつつあります。この変化によって、ユーザーは「特定のキーワードを入力してページを探す」のではなく、会話形式で自分の課題や疑問を解決するスタイルを取るようになっています。
製造業サイトにおいては、単に「技術名」「加工方法」の説明を羅列するだけでは不十分です。 「その技術でどんな課題を解決できるのか」「その加工方法はどういった状況で活用されるのか」といった文脈情報を豊富に掲載することで、AI検索の回答に取り上げられやすくなります。
課題解決型のコンテンツの制作
これからのSEOにおいて重要になってくるのは、顧客の課題に直結したコンテンツを発信することです。製造業の購買担当者や技術者は、「材料名」や「加工名」で調べるだけでなく、次のような形で検索しています。
- 「アルミ部品の軽量化 加工方法」
- 「ステンレス溶接 歪みを抑える方法」
- 「小ロット試作 精度保証の方法」
つまり、ユーザーが抱えている「困りごと」や「目的」に合わせた改題解決型のコンテンツの提供が求められるのです。製造業サイトで技術について深掘りするコラム等のコンテンツの制作をすることもありますが、技術コラムや事例紹介だけにとどまらずに、直接のトラブル解決事例を積極的に公開し、SEOのキーワードの幅を広げることが重要になってきています。
まとめ
製造業SEOは「アクセス数」ではなく「成果を出すキーワード選び」
SEO施策を進める中で、多くの企業が「アクセス数の増加」を目標に掲げがちです。しかし、製造業においては単にアクセスが増えても、それが必ずしも問い合わせや受注につながるわけではありません。重要なのは、「誰に」「どんな目的で」見てもらうかという視点です。製造業のSEOにおいては「アクセス数」ではなく、問い合わせや商談につながる成果を生むキーワードを選定することが最も重要なのです。
成果につながるキーワード戦略を継続的に見直す
市場のニーズや検索傾向は常に変化しています。特に製造業では、新しい技術や加工方法が登場することで、数年前までは存在しなかった検索キーワードが新たに需要を生むケースも少なくありません。そのため、一度決めたキーワードを放置するのではなく、定期的に見直すことが必要です。
- Google Search Consoleを活用して、実際に流入している検索ワードを分析
- 競合他社が狙っているキーワードや新規に伸びているキーワードを調査
- 自社の強みに関連する新しい検索意図の洗い出し
これらを繰り返すことで、常に「今の市場」と「自社の強み」にマッチしたキーワード戦略を維持できます。SEOは一度の施策で終わるものではなく、継続的に見直し・改善するプロセスこそが成果を生み出す最大のポイントです。