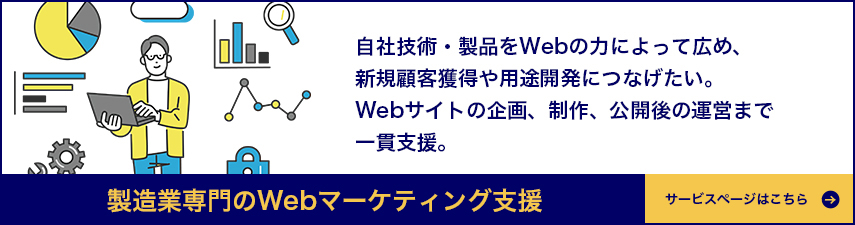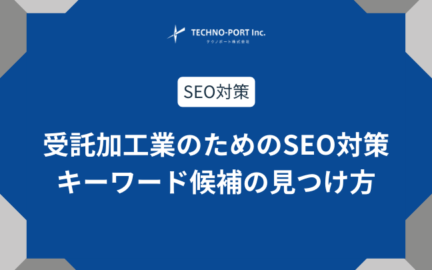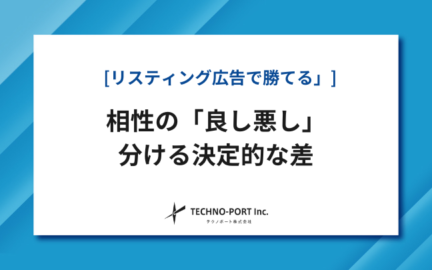AIによる情報収集が主流化になりつつある今、生成AI(ChatGPT・Geminiなど)への自社情報の最適な表示が、企業の信頼性やブランド認知に直結します。本記事では、LLMOをはじめ、GEOやAEOといった呼称の違いや意味を明確に整理し、SEOとの違いや、なぜ今LLMO対策が必要か、そして具体的な対策方法までを解説します。
この記事の目次
AI時代のSEO
AI検索が普及しつつある2025年現在、ユーザーの検索体験は多様化してきています。ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIや、GoogleのAI Overviewに代表される「AIによる要約表示」により、ユーザーはWeb画面を訪れずに情報を入手する傾向が強まっています。実際、調査によれば80%のユーザーが40%をリンククリックなしで完結させており、Webサイトへのトラフィックは減少傾向にあります。
このような背景のもと、従来のSEOに加え「AIに引用されるコンテンツ」を目指す新たな最適化戦略が求められています。つまり、AI検索の回答文内で自社ブランドや製品が自然に言及されることが、新しいブランド認知の機会となってきているのです。
LLMO、AEO、AIO、GEO
近年出てきたということもあって、AIに関する検索対策の言葉が複数同時に誕生しています。それぞれについて微妙に意味合いが違いますので、ここで整理しておきたいと思います。
LLMO(Large Language Model Optimization)
- 大規模言語モデル(LLM)に対して、自社のコンテンツがChatGPT・Gemini・Claude などのAI回答内で引用されやすくなるよう最適化する施策です。
- 本質的には、AIに自社情報を“信頼できる情報源”として認識させる戦略であり、AIOとほぼ同義に理解されることもあります。
AIO(AI Optimization)
- AI(生成AIや検索AI、音声アシスタントなど)全体に対する情報最適化を指し、LLMOより広義の概念です。
- LLMO が大規模言語モデル(LLM)を対象とするのに対し、AIO はAI全般に向けた最適化を指します。
GEO(Generative Engine Optimization)
- Google SGE(AI Overview)や Perplexity、Bing Chat といった生成型AIエンジン全体において、自社情報が生成される回答に自然に組み込まれるよう工夫する対策です。
- 大規模言語モデル(LLM)ではなく生成エンジン全体にアプローチする意味で、LLMOより広い視点を持ちます。
AEO(Answer Engine Optimization)
- 検索エンジンやAIチャットがユーザーの質問に対して直接的な回答を提示する場面(強調スニペットや要約回答など)において、自社が“最適な答え”として表示されるようにコンテンツ設計する施策です。
- ゼロクリック検索の文脈で特に重要視される最適化手法です。
LLMOをするの目的
今回の記事では上記の中でもLLMOに焦点を当てて紹介します。LLMOは単なる検索順位対策ではなく、生成AIが回答を生成する未来の検索空間で、自社情報を積極的に露出させるための戦略的アプローチです。まずはLLMOに取り組む目的について整理をしたいと思います。
AI回答内で自社情報を引用・言及されるようにする
LLMOの主な目的は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIがユーザーのクエリに回答を生成する際に、自社のWebページやブランド情報が信頼できる情報源として選ばれることです。これにより、AI経由のブランド露出や認知向上を狙います。
ブランド認知の機会拡大と指名検索の促進
AIによる要約表示やチャット式回答が主流化する中で、従来のクリック型トラフィックではなく、AI回答内での言及による認知接点を増やすことが重視されています。これにより指名検索、最終的なWebサイト訪問・コンバージョンにつなげます。
コンテンツの可視性と理解可能性向上
自然言語処理モデルがより正確にコンテンツを理解・利用できるよう、構造化データや明確な情報設計(FAQ/表/結論ファースト構造など)を通じて、AIへの抽出と参照を助ける構造にすることで、ユーザーから見てもわかりやすいコンテンツの生成を促すことができます。
SEO vs LLMO の主な違い
これまでのSEOとLLMOについて、おおよそは同じですが、下記のような違いがあります。
1. 対象読者の違い
- SEO:検索エンジン(Googleなど)を第一ターゲットとし、検索結果での視認・流入を狙う。
- LLMO:生成AI(ChatGPTやGeminiなど)を第一読者と想定し、AI回答時の引用を狙う。
2. 最適化目標の違い
- SEO:検索結果ページでの順位向上・クリック率・オーガニック流入を最大化
- LLMO:AIが生成する回答に自社情報やブランドが自然に含まれることで、「ブランド想起」や「信頼性」の獲得につなげる。
3. 情報処理手法の違い
- SEO:キーワードマッチ、被リンク、ページ構造などによって内容を評価
- LLMO:自然言語理解や文脈的関連性に基づき、意味を正しく解釈されやすい構造が重要
4. 両者の関係性
- LLMOはSEOを置き換えるものではなく、SEOを基盤にした拡張的手法
- SEOで構築された信頼性(E‑E‑A‑T)や技術的健全性が、LLMOでAIに信頼されるための前提となる
LLMO対策の具体的手法
LLMO時代に必要な対策として、大きく以下の2つが挙げられます。
顧客課題と解決事例の構造化コンテンツ制作
- 課題→解決策を示すコンテンツを作成
- 見出しに課題を明記、冒頭で解決の結論提示、その後の段落で具体的技術と成果を記載
- AIが「出典として取り出しやすい形式」に整えていくことが必要
FAQ形式や定義型コンテンツの導入と構造化
- よくある質問形式の記事(FAQ)コンテンツを、FAQなどで構造化
- AIや検索エンジンが「回答候補」として抽出しやすい形式に設計することで、AEO的な効果も期待できる
2つ共に共通する内容として、質問と答えがワンセットになるような形のコンテンツの作成が必要ということです。
まとめ
生成AI(ChatGPT・Geminiなど)による検索体験が主流となった現代では、従来のSEO対策に加えてAIに対しても対策が必要になってきているといわれています。
ただし、ChatGPTに代表されるような生成AIの主な回答については、対象のキーワードで上位20位までのウェブサイトの内容で構成されているという調査結果も出ており、SEOの対策をしっかりしておけばLLMOの対策になるという意見も出ています。
これから先、AIを使った検索行動がどんどん主流になってくる流れは避けられない中、弊社としてもどのように検索行動が変化していくのかを注視し、最新のトレンドを取り入れていく予定です。