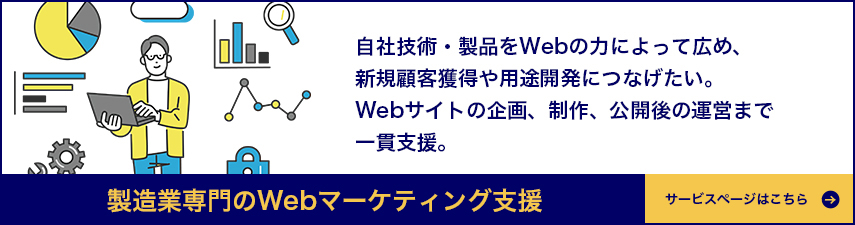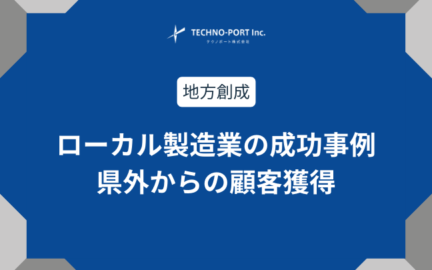製造業を取り巻く環境が大きく変化する中、既存事業の限界や、EVシフトなど業界構造の変動による影響を受け、新規事業の立ち上げを検討されているメーカー様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。弊社でも近年、新規事業の方向性のご相談や、立ち上げ後のWebを活用した拡販方法についてご相談をいただくことが増えてきています。
本記事では、新規事業の立ち上げを検討されている方に向けて、メーカーにおける新規事業モデルを手法別に解説し、実際に新規事業を立ち上げるステップや、立ち上げた事業をWebを活用して拡販する戦略についてご紹介します。
この記事の目次
メーカーの5つの新規事業モデル事例
従来の「モノ(製品)を売る」枠組みを超えて提供方法を工夫したり、サービス範囲を拡大したりすることで新たな価値を提供できます。ここではメーカーが取り組みやすい新規事業モデルを5つ紹介します。
アフターサービスの導入
自社製品導入後のメンテナンスや、使用状況に合わせた提案をするモデルです。製品を売ったきりで終わってしまっていた顧客との接点を持ち続けることができ、安定的なビジネスチャンスを確保することができます。
建機メーカー:修繕タイミングの提案システム
■ コマツ (Komtrax)
ICT技術を活用したKomtraxというシステムにより、建設機械を「故障してから直す」ではなく、「異常を予兆し、修繕のタイミングを先回りして提案する」といったアフターサービスを展開。世界中で稼働するコマツ機にリアルタイムな稼働データと保全提案を届けています。
料金体系の変更
技術や製品そのものは変えずに、料金体系を見直すモデルです。近年BtoB製造業でも、実使用量に応じて課金する従量課金型や、単発売り切りではなく継続課金で価値提供するサブスクリプション型が注目されています。
レーザー加工機メーカー:部品単位での課金型サービス
■ TRUMPF
レーザー加工機メーカーである同社は、高額設備を導入したものの稼働率が伸びず悩むユーザーに対し、加工完了した部品単位で従量課金するサービスを提供。設備投資無しに最新鋭マシンを使えるため、小ロット・多品種の需要を抱えるサプライヤーに高い需要があります。モニター顧客への実施では、生産性が最大50%向上したとの結果も挙げられていました。
オプション型プランの提供
従来はセットで売るような製品を、オプションとして分けて販売させるモデルです。顧客が必要な機能だけを選択して購入できるため、ストレスなく柔軟に導入することが可能となります。
建機メーカー:アタッチメントツールのオプション提供
■ Caterpillar
基本機械(ショベル・ホイールローダなど) の販売に加え、ブレーカー、グラップル、除草セーバーなど35 種類以上のアタッチメントをオプション型提供。後付けでも簡単に交換・装着可能なため顧客はそれぞれの現場用途に応じて導入ができます。
同業界の売買仲介
自社が属する業界内で業界内の売り手・買い手をマッチングするビジネスモデルです。業界の専門知識やネットワークを活かして取引の場を提供し、仲介料を得るといった利益面の他に、自社のポジション向上や市場ニーズのデータ蓄積といった副次的なメリットも期待できます。
化学メーカー:天然素材の売買マッチングサイト
■ 住本化学株式会社 – (Biondo)
化学メーカーである同社のノウハウにより、素早く高度な分析技術を提供し、素材を売りたい人と買いたい人をつなぐデジタルサービスを展開。買い手は成分の詳細分析データを確認しながら直接取引できるため、購買リスクを最小化できます。
コミュニティの構築
自社の顧客をコミュニティ化させ、製品に関する情報共有やイベントを実施させるモデルです。コミュニティ自体が直接的な利益を生み出さなくとも、疑問をすぐ解決できる利便性や顧客同士の交流により、製品利用の継続率が上がること(自社から離れない)が期待されます。
電機メーカー:ユーザーと開発者の交流プラットフォーム
■Siemens(シーメンス)- Xcelerator Community
PLC・CNC制御・工場オートメーション領域において、ユーザー・SIer・開発者が公式技術スレッドで交流。専門チュートリアル、製品ロードマップへの意見投稿、共通課題の知見共有などが可能です。
メーカーが新規事業を立ち上げるためのステップ
新規事業モデルのアイデアが見えてきたら、次はそれを具体化し事業として軌道に乗せるプロセスです。場当たり的に動くのではなく、段階的に準備を進めることで成功率を高められます。メーカーが新規事業を立ち上げる際の一般的なステップを、以下に5つに整理しました。
市場ニーズ、競合事業の調査
まずは狙おうとしている市場のニーズを徹底的にリサーチします。顧客がどんな課題を抱え、どんな製品・サービスを求めているのか、最新の市場動向を把握しましょう。また既に似たサービスや競合他社の動向も調べ、参入機会や差別化のポイントを見極めます。市場規模や成長性、参入障壁の高さも調査し、取り組む方向性に優先順位を付けると良いでしょう。
自社の立ち位置の整理
次に、自社の強みやリソースを洗い出します。保有技術や設備、顧客基盤のほか、弱みや制約も再認識した上で、新規事業に活かせる経営資源と足りない要素を明確化します。自社が市場でどんな立ち位置・価値提供ができるかを見定め、自社の強みとステップ1で調査した市場ニーズとの交点を探りましょう。この段階で「自社の技術によってどんな価値を提供できるのか」を顧客視点で捉え直すことが重要です。
ビジネスモデルの検討
市場ニーズと自社の強みのマッチングから、新規事業の具体的なビジネスモデルを構築します。提供する製品・サービスのコンセプト、収益モデル(どのように課金するか)、販売チャネル、必要なパートナーやリソースなどを総合的にデザインしましょう。可能であればビジネスモデルキャンバス等のフレームワークを活用し、価値提案・顧客セグメント・コスト構造・収益構造を視覚化すると抜け漏れが減ります。またアンゾフの成長マトリクスを活用し「既存市場・新市場・既存製品・新製品」の4象限で発想してみると、事業アイデアの方向性が整理できます。
小規模な実証(PoC)とフィードバック収集
検討したビジネスモデルは、いきなり大規模投資して本格展開する前に、小さく試験的に試すことで検証するのが鉄則です。プロトタイプの開発や限定した顧客へのPoC(概念実証)提供を行い、想定通りの価値提供ができるか、改善点はないかをチェックします。可能であれば既存の親しい顧客や業界内の知り合い企業に協力を仰ぎ、モニター価格でサービスを試してもらうのも有効です。実際に使ってもらうことで初めて見えてくる課題や、ユーザーが真に喜ぶポイントが明確になります。PoCの結果得られたフィードバックをもとに、製品・サービス内容や価格設定、オペレーション体制を調整し、事業計画をブラッシュアップしていきます。
販売チャネルの整備、本格展開
テストマーケティングで事業の手応えを掴んだら、いよいよ本格的にサービス提供を開始します。その前に、販売チャネルとマーケティング施策をきちんと整備することが重要です。自社サイトでの情報発信や問い合わせ対応体制、営業担当者へのトレーニング、必要に応じ代理店網の構築など、顧客がスムーズにサービスを利用できる環境を用意します。またプレスリリースの配信や展示会出展、既存顧客へのメール案内など、新サービスの存在を広く周知する活動も欠かせません。特にWebを活用すれば比較的低コストで見込み客にリーチできるため、後述するようなデジタルマーケティングも駆使してスモールスタートから段階的に事業規模を拡大することをおすすめします。
Webを活用した新規事業の拡販戦略
新規事業を軌道に乗せるには、効率的なマーケティングによって見込み顧客を開拓し、売上につなげていく必要があります。中でもWebを活用したテストマーケティングや情報発信は低コスト・短期間で実施でき、顧客の反応をデータで測定できるため非常に効果的です。大きな投資を行う前に、Web上で市場の声を収集してビジネスモデルの妥当性を確認し、軌道修正することで成功確率を高められます。以下に、新規サービスをWebで拡販していく流れを説明します。
サービス紹介用のコンテンツを作成
まずは自社のWebサイト上に、新規事業のサービス内容を紹介するページやランディングページ(LP)を用意します。サービスの狙いや特徴、導入メリットなどユーザーに伝えたい要点を整理し、わかりやすいコンテンツを作成しましょう。重要なのは、ユーザーがそのサービスを導入することで得られる価値を明確に打ち出すことです。なお初期段階で時間をかけてページを作り込むよりも、まず公開して反応を見てから改善する意識が大切です。公開後にアクセス解析や問い合わせ状況を見ながら、コンテンツや導線を適宜ブラッシュアップしていきましょう。
一部ユーザーへテスト実施・検証
Web上でサービス内容を公開したら、次に実際の顧客に使ってもらうテストマーケティング段階に進みます。既存顧客や業界ネットワークから数社を選び、パイロットユーザーとして新サービスを導入提案してみます。期間限定の無料トライアルや特別価格を提示し、ハードルを下げて協力を募るのも有効です。テスト導入を通じて得られたリアルなフィードバック(使い勝手の問題点や予想以上に評価された機能など)は、サービス改良の貴重な手がかりとなります。Webサイト上にもテスト事例やユーザーの声を掲載できれば、信頼性向上につながります。この検証フェーズを経てサービス内容に自信が持てたら、本格展開に移りましょう。
対外的に広く情報発信
準備が整ったら、Webを駆使して新規事業の存在を世の中に広く発信していきます。具体的には、まず自社の既存取引先や見込み客に向けてメールマガジンやニュースリリースでサービス開始を告知します。またプレスリリースを配信して業界ニュースとして取り上げてもらったり、関連キーワードで検索上位を狙うSEO対策を講じたりすることも有効です。必要に応じてリスティング広告やSNS広告を活用し、ターゲット層への露出を増やします。限られたマーケティング予算の中で最適な手段を選ぶには、各施策の特性(費用感や効果が出るまでの期間、リーチできる層など)を踏まえて検討しましょう。これらのオンライン施策と並行して、展示会への出展や業界団体での発表などオフライン施策も組み合わせれば、新規事業の認知拡大とリード獲得に相乗効果が期待できます。
以上、メーカーが取り得る新規事業モデルの種類から、立ち上げプロセス、そしてWeb活用による拡販方法までを広く紹介しました。自社の現状と照らし合わせ、「まずはこのモデルから試してみよう」「このステップが抜けていたかもしれない」など感じられるヒントとなれば幸いです。