この記事の目次
変革期を迎える自動車部品業界
自動車部品業界は現在、歴史的な転換点を迎えています。エンジン車から電気自動車(EV)へのシフトが加速する中、市場構造が根本から変化し、多くのサプライヤー企業が生存戦略を模索しています。EVへの移行により自動車部品点数は約3万点から約2万点へと激減し、特にエンジン関連部品メーカーでは事業継続が困難となり、廃業に追い込まれるケースも増加しています。この危機的状況を乗り越えるには、自動車業界の枠を超えた「異業種展開」が不可欠となっています。
ただ、実際に異業種の開拓を行おうとしても、なかなか思うような成果が出ていないという声を非常に多く聞きます。
本稿では、自動車部品サプライヤーにとって異業種開拓がなぜ急務なのか、解決策としてWebマーケティングでの新たな販路開拓の有用性について解説します。
異業種開拓のための無料相談・無料で企画戦略作成
私たちテクノポートでは、自動車部品メーカー様向けに異業種開拓のための無料相談サービスを提供しています。
無料相談では、まず御社の現状の事業分析から着手し、狙える市場の市場調査や競合他社の競合分析を行ったうえで、最適な新規事業戦略の企画立案まで一緒に考えます。
自動車部品サプライヤーが直面する構造的課題
EVシフトの加速により、部品サプライヤー各社は以下のような深刻な課題に直面しています:
- 主要市場の急速な縮小:ガソリン車関連需要の減少が顕著となり、エンジン部品やトランスミッション部品の売上が大幅に低下
- 技術革新への対応遅れ:モーター、バッテリー、インバーターなどEV特有の部品や、軽量化素材、熱管理技術といった新領域への開発投資が追いつかず、競争力が低下
- 収益性の悪化:完成車メーカーからの価格引き下げ圧力が年々強まり、従来のビジネスモデルでは利益確保が困難に
これらの課題から明らかなように、「自動車部品専業では将来的に事業継続が困難」という現実に業界全体が直面しています。特にエンジン関連部品はEV化によって需要が激減するため、自動車メーカーのEVシフトが進むほど下請け部品メーカーへの影響は甚大です。すでに大手部品メーカーの中にはエンジン部品事業を売却し、EV事業へと舵を切る企業も増加しており、中小サプライヤーにとっては生き残りをかけた戦略的転換が喫緊の課題となっています。
異業種展開の必要性と意義
主力市場が縮小傾向にある現状において、異業種への展開は「選択肢」ではなく「必須戦略」といえます。自社の保有する高度な加工技術や製品技術を、医療機器、産業機械、航空宇宙、エネルギー、インフラなど自動車以外の産業分野に応用することで、新たな成長機会を創出できます。
実際、日本政府や自治体も自動車部品メーカーの事業転換を重要政策課題として位置づけ、2025年度には経済産業省が「自動車部品サプライヤー事業転換支援事業(ミカタプロジェクト)」を立ち上げ、中小サプライヤーの異業種展開・EV領域参入を強力に後押ししています。業界全体が「待ったなし」の状況に置かれているのです。
しかし、新分野への参入には多くの障壁が存在します。現場からは次のような課題が頻繁に報告されています:
- 新規販路開拓のノウハウ不足:長年、限られた取引先との関係に依存してきたため、異業種の潜在顧客へのアプローチ方法が分からない
- 従来型営業手法の限界:展示会出展や飛び込み営業を実施しても名刺交換で終わり、実質的な商談に発展しない。紹介やコンサルタント経由での企業紹介も成約率が低い
- 経営資源の制約:特に中小企業では専任の営業・マーケティング人材が限られており、新規市場の調査や戦略策定に十分なリソースを割けない
こうした状況を打開し、効果的に異業種顧客を獲得するための有力な手段として、Webマーケティングの戦略的活用が注目されています。
異業種開拓の成功させた事例3選
事例1. 株式会社長野サンコー(プレス金型・プレス加工)
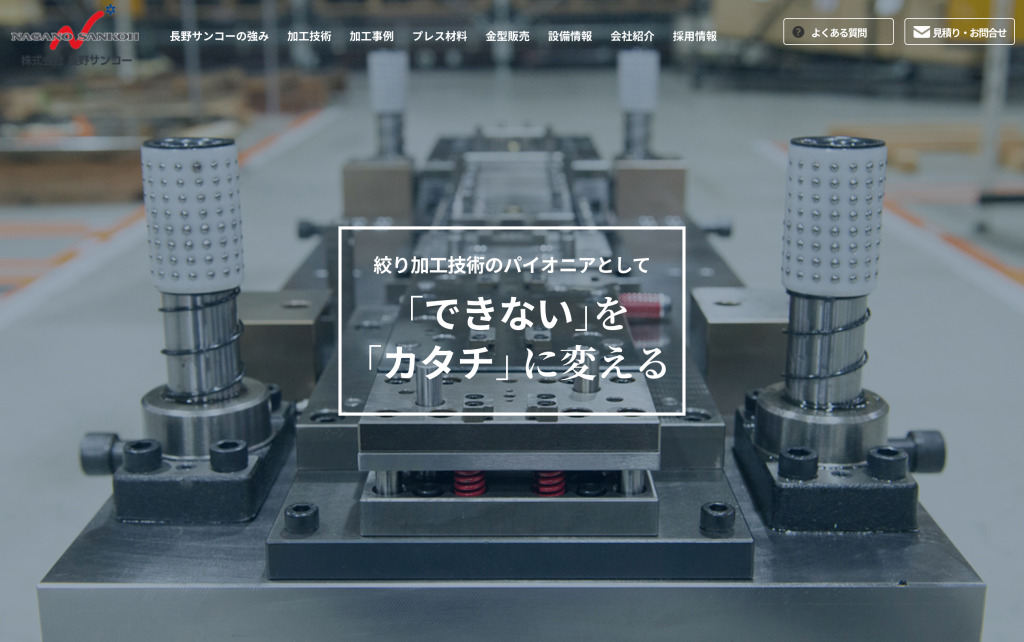
| 事業内容 | プレス金型の設計・製作およびプレス加工 |
| サイトURL | https://www.naganosankoh.jp/ |
| 施策内容 | Webサイト制作、SEO対策 |
抱えていた課題
以前よりWebマーケティングを実施していた同社。しかし、目指していたのがインターネット上で取引される案件数が絶対的に少なく、受注難度が高いとされる量産案件の受注だったため、なかなか見合う案件の引き合いを獲得できずにいました。
実施したWebマーケティング施策
難度の高い量産案件を獲得するためには、相当数のアクセスユーザをWebサイトへ呼び込む必要があると考え、「絞り加工」や「プレス金型」といった検索需要が大きく、SEO難度の高いキーワードによるSEO対策が必須と考えました。難度の高いキーワードによるSEO対策を成功させるために、自社の技術紹介だけではなく、その技術に関する解説コンテンツを弊社にて執筆し掲載すると共に、大量の加工事例を掲載することで、コンテンツリッチなWebサイトへとリニューアルしました。
Webマーケティング施策の成果
対策キーワードでの検索上位表示を実現し、業種問わず多くの引き合い獲得に成功しました。その結果、Webサイトのリニューアルから1年経たずして、超大型の量産案件の受注を達成することができました。
事例の詳細は以下からご覧いただけます。
事例:Webマーケティングでは難易度の高い量産案件の受注に成功
事例2 荒川技研株式会社(プラスチック加工)

| 事業内容 | プラスチック加工 |
| サイトURL | https://www.a-giken.co.jp/ |
| 施策内容 | Webサイト制作、SEO対策、コンテンツマーケティング、アクセス分析・改善 |
抱えていた課題
同社は従来、自動車業界やアミューズメント業界のメーカーとの既存取引による売上が大半を占めており、当面の業績には危機感がありませんでした。しかし、自動車業界ではEV化による構造変化が進行し、アミューズメント業界にも衰退の兆しが見え始めるなど、将来の不確実性が高まっていました。
こうした状況を踏まえ、将来を見据えた新規顧客開拓の必要性は認識していたものの、「Webマーケティングが重要であることは理解しているが、何から始めればよいのか分からない」という状態が続いていました。
実施したWebマーケティング施策
同社は、切削加工・真空注型・光造形といった幅広いプラスチック加工技術を有していましたが、対応領域が多岐にわたるがゆえに、顧客にとっての「得意分野」が見えにくくなっていました。そこで、戦略的にターゲットを「樹脂試作」に絞り、「プラスチック試作の専門工場」というキャッチフレーズで明確な訴求を図ることにしました。
Webサイト公開後は、アクセスデータの分析や問い合わせ内容の検証を継続的に行い、需要の強い分野を特定。それに合わせた設備投資を行うことで、より専門性の高いニーズにも対応できる体制へと段階的にシフトしていきました。
加えて、コンテンツマーケティングにも注力。樹脂の基礎知識や材料特性などの技術情報を発信することで、専門性の高さを訴求し、潜在顧客への認知向上を目指しました。「プラスチック加工といえば荒川技研」と第一想起される存在となることを目標に、Web上でのブランディングを強化しています。
Webマーケティング施策の成果
施策の結果、問い合わせ件数は大幅に増加し、特に異業種からの引き合いが顕著となりました。それに伴い、取引社数は数百社規模へと拡大。多い時期には、毎日のように新規問い合わせが寄せられるなど、Web経由での商談機会が飛躍的に増加しました。
事例:数百社の新規取引先開拓に成功。得意領域を見出し訴求力アップ
事例3 有限会社小林製作所(プレス板金・切削加工)
のエキスパート-www.ksx_.jp_.jpg)
| 事業内容 | 金属プレス板金・金型設計製作・切削加工 |
| サイトURL | https://www.ksx.jp/ |
| 施策内容 | SEO対策、Webコンサルティング、Webコンテンツの制作 |
抱えていた課題
10年前、弊社は通信機器インフラ関連の特定1社からの売上が全体の80%を占めており、企業としての経営基盤が極めて偏った状態にありました。このリスクの高い状況を打開するため、「1社依存からの脱却」を経営課題に掲げ、積極的な営業活動に取り組んできました。
当時の営業手法は、展示会や商談会、取引先からの紹介が中心でしたが、思うような成果には結びつかず、「顔合わせで終わるだけ」というケースも多く見受けられました。また、弊社はプレス・板金・切削など幅広い加工に対応できる強みがある一方で、「何が得意なのか」が伝わりにくく、特徴を打ち出しづらいという課題も併せ持っていました。
Webマーケティングを活用した成果
こうした課題に対する解決策の一つとして、HPの活用を本格化。現在では、月平均30件の問い合わせを獲得するまでに至り、過去10年間で100社以上の新規顧客の開拓に成功。結果として、特定企業への依存状態からの脱却を実現しました。
ただし、これらの成果はHP単独の力によるものではありません。お問い合わせの段階では成約に至らなかった案件も少なくありませんが、弊社ではその後も関係性を維持し、別案件での受注へとつなげる地道な営業努力を継続しています。
つまり、HPはあくまでも「顧客接点を生み出すための強力なツール」であり、成果を生むには対面での営業活動との連携が不可欠です。とりわけ、従来の営業手法では接触が難しかった大手メーカーとの接点創出にもつながっており、その有用性を強く実感しています。
事例:1社依存からの脱却!10年間で100社以上の新規顧客開拓に成功
異業種開拓におけるWebマーケティングの有効性
事例の一部を紹介しましたが、テクノポートでは、多くの企業の異業種展開の支援を行ってきました。その取り組みの中で言えることは、異業種展開を成功させる上で、Webマーケティングは極めて効果的なアプローチです。その理由を3つの観点から検証します。
1. 企業の購買行動変化への対応
まず理解すべきは、BtoB取引における「探索・発注プロセス」が根本的に変化している点です。従来は人脈構築や飛び込み営業、展示会などオフライン中心の取引先開拓が主流でしたが、現在では発注側企業もデジタルチャネルを通じた情報収集が標準となっています。
市場調査によれば「BtoBの購買担当者の67%は営業担当者と接触する前に購買プロセスの大半を完了しており、64.8%が業務上必要な製品・サービスの主要情報源として企業Webサイトを活用している」という結果が出ています。製造業分野においても「製品選定時に検索エンジンで情報収集する」担当者が75%、「企業Webサイトの情報を参考にする」担当者が58%に達し、従来型の営業活動や展示会よりもデジタル情報を重視する傾向が顕著です。
つまり、企業がHPをうまく活用できていなければ、潜在顧客から「存在しないも同然」と判断される可能性が高まっています。
逆にWebマーケティングを効果的に活用すれば、これまで接点のなかった異業種企業からの問い合わせ獲得機会が飛躍的に増大します。適切なSEO対策により検索エンジンでの発見可能性を高めることで、自動車業界の枠を超えた新規顧客との接点を創出できるのです。
引用:テクノポート:大手メーカー設計開発者へのアンケート調査
2. 効率的な新規リード獲得の実現
Webマーケティングのもう一つの強みは、限られた経営資源で最大限の成果を生み出せる点にあります。自社Webサイトにおいて技術ブログや導入事例を充実させ、異業種の見込み客が検索しそうなキーワードで上位表示されれば、24時間365日休むことなく見込み客を集客できます。
さらにオンライン問い合わせフォームや技術資料ダウンロードページを設置することで、単なる名刺交換で終わらせず、能動的にアクションを起こした「顕在化した見込み客」のリストを構築することが可能になります。
このアプローチにより、従来の「待ち」の営業スタイルから、情報提供を通じて見込み客の関心を引き出す「攻め」の営業スタイルへと転換できます。異業種の潜在顧客に対してこちらから価値ある情報を提供し、興味を示したタイミングで的確にアプローチする——こうした新しい営業モデルを構築することで、これまで困難だった異業種開拓の突破口を見出すことができます。
3. 技術軸や機能性軸のキーワード対策は異業種への訴求の切り口になる
自動車業界に所属しているとしても、保有する技術や提供できる機能性軸に視点を変えれば、それは異業種でも当たり前のように使われている技術は多くあります。つまり技術や機能性軸での訴求をすることによって、自動車以外の業界からの問い合わせを呼び込むチャンスはいくらでも生み出せるのです。
「あの業種のあのような仕事に参入したい」という考えをしてしまうと、ターゲットが限られてしまい、既存業者よりも提供価値の高いものを訴求せねばとなってしまいます。そこまでの競争優位性を出せる価値を定義することはできずに行き詰ってしまいます。たとえツテをたどって商談に持ち込めたとしても、機会があればお願いで終わるケースも非常に多いです。
ターゲットを絞り提供価値を明確化する取り組みも大切ですが、サプライヤー企業にとっては、幅広いユーザーに自社の技術の存在を認知させ、必要と感じ相談を呼び込む取り組みが非常に重要です。
異業種開拓を成功させるWebマーケティングのポイント
異業種向けのWebマーケティングを効果的に行うために、以下のようなポイントに留意しましょう。
自社技術・製品の棚卸
まずは自社が持つ強みや独自技術を洗い出します。他業界でも通用しそうな要素は何か、逆に現状のままでは不足している要素は何かを整理しましょう。例えば「微細加工技術」「○○認証取得済み」「年〇万個の大量生産対応可」など、異業種の企業にアピールできる強みを見極め、それを軸に売り込み戦略を立てます。
キーワード需要調査
次に、狙いたい異業種分野でどんなキーワードが検索されているかを調べます。Googleキーワードプランナー等のツールを使えば月間検索ボリュームが分かりますし、業界の人々が普段使う用語のリサーチにもなります。「○○ 外注」「○○ サプライヤー」「○○ 協力会社」など、自社の技術とマッチするニーズを探り、狙うべきキーワードを絞り込みましょう。
コンテンツ作成とSEO対策
調査で見つけたキーワードをもとに、自社サイトに関連コンテンツを用意します。先述のブログ記事や技術資料の公開などです。重要なのは、ただ製品を宣伝するのではなく相手の課題を解決する情報提供を意識すること。例えば「〇〇業界向け△△加工のポイント」といった記事で自社ノウハウを公開すれば、読むだけで役立つ内容にターゲット層は惹きつけられ、自社への信頼感も高まります。またページのタイトルや見出し、メタディスクリプションにキーワードを盛り込むなどSEOの基本も押さえつつ、読みやすい文章・レイアウトを心がけましょう。
効果測定と改善
Webマーケティングはやりっぱなしにしないことも大切です。Googleアナリティクス等の解析ツールでアクセス数や問い合わせ数の推移をチェックし、うまくいっている施策・いない施策を見極めて改善を続けましょう。例えば「Aという記事はアクセスが多いのに問い合わせに繋がっていないなら、記事末にCTA(お問い合わせ誘導)を追加してみる」など、小さな改善の積み重ねで成果は着実に向上します。データに基づいて施策をPDCAサイクルで回すことで、限られたリソースでも効率良く異業種開拓を進めることができます。
これらのポイントを意識しながらWeb上での発信と集客を強化していけば、着実に問い合わせを伸ばすことができます。
勘違いされやすいHPリニューアルの注意点
Webに力を入れようということでHPをリニューアルする企業は非常に多いです。しかし、勘違いしてはいけないのがリニューアルをすればよいというわけではありません。
自社の提供価値を明記することは当然重要で、しっかり戦略を立てたとしても、どうやって集客をするかという視点が抜けているとまったく効果が出ません。極端な話、戦略よりも集客施策のほうが重要なのがWebの世界です。だれも訪れない場所で、どんなに魅力的な取り組みをしていても意味がないからです。
費用を抑えて集客できるのがSEO対策と呼ばれる検索上位対策です。「どのようなキーワードで見られたいか」「どのようなキーワードに需要があるのか」「そのキーワードで対策するためにどのようなページを作ればよいか」という点を徹底的に突き詰め戦略と施策を結び付ける必要があります。
そこができていないと、「せっかくHPをリニューアルしたのに、問い合わせがまったく来ない」という状態に陥ってしまいます。
逆にリニューアルせずに、集客施策を見直すだけで成果を出している会社もたくさんあります。
リニューアルしたから集客できる”と考えるのは早計です。
異業種開拓のための無料相談・無料で企画戦略作成
私たちテクノポートでは、自動車部品メーカー様向けに異業種開拓のための無料相談サービスを提供しています。
無料相談では、まず御社の現状の事業分析から着手し、狙える市場の市場調査や競合他社の競合分析を行ったうえで、最適な新規事業戦略の企画立案まで一緒に考えます。
もちろん、「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。異業種への一歩を踏み出そうとする皆さんを全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!






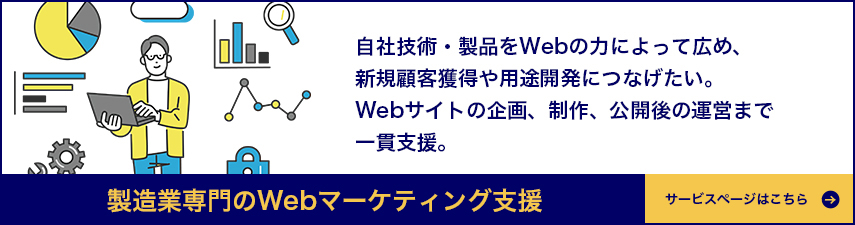
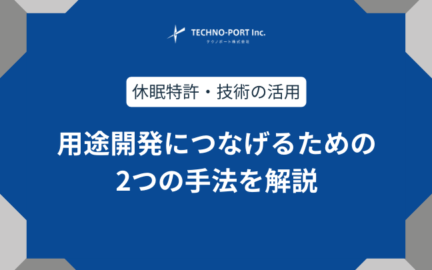
-1-432x270.png)

